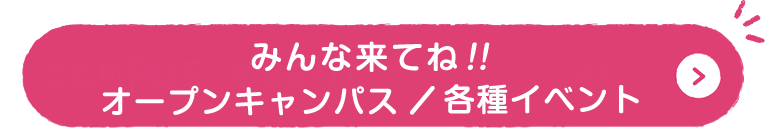福岡の女子大学|筑紫女学園大学
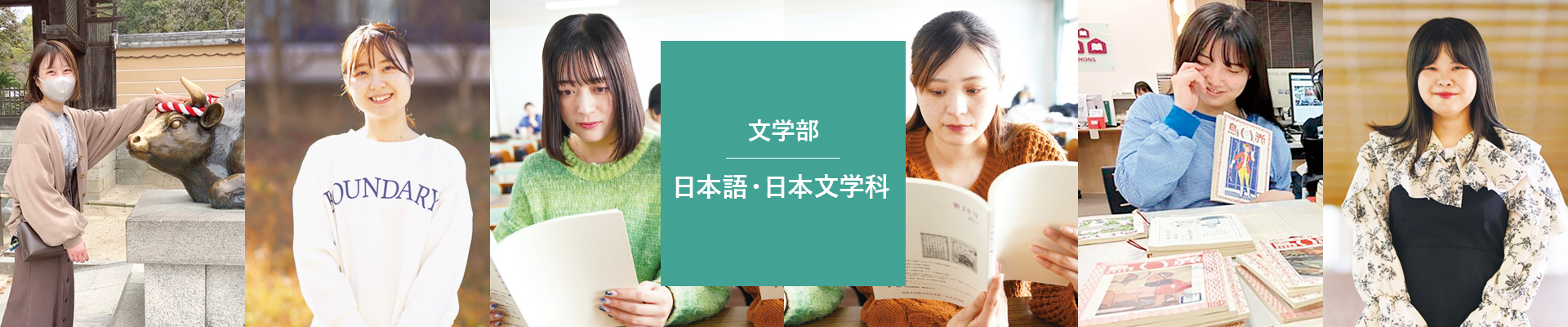
学芸員課程主催「筑紫想い出カフェ2024公開報告会」が開催されました
- 2024年12月30日 -

11月28日(木)文学部学芸員課程主催「筑紫想い出カフェ2024公開報告会〜回想法を使った地域課題の発⾒と解決」が開催されました。
この企画は⼤津忠彦(本学⾮常勤講師)の「博物館資料論」の特別授業を、公開講座も兼ねて一般に公開する形で毎年開催されています。
今年のテーマは「地域課題の発見→解決~想い出キットでお年寄りと子供をつなぐ~」でした。1年をかけて取り組んだ学芸員課程3年生有志5名を代表し、日本語・日本文学科3年生の小野さん、中村さん、木下さんの3人が報告を行いました。
まずはじめに「回想法」についての概説がありました。
「1960年代にアメリカの精神科医ロバート・バトラーが提唱した一種の心理療法である。マンツーマンで行う個人回想法と、10人前後で行うグループ回想法があり、昔の写真や音楽、生活用品などを見たり触れたりして昔の思い出や経験を語り合うことで、脳が活性化し、認知症の進行の予防効果があるとされている。(参考:公益財団法人長寿科学振興財団「健康長寿ネット 回想法」)」
次に今年度の「想い出カフェ」の実施にいたるまでの経緯についてまとめてくれました。
「博物館学芸員が取り組むべきとされる『地域の課題解決』について学ぶため、地域の活性化のため高齢者を中心とした回想法に取り組む目的で、筑紫女学園大学博物館学芸員課程の先生と学生で「想い出カフェ」と称し、ボランティアを開始。これまで10年に亘る活動歴がある。今年は5人のメンバーで取り組み、『高齢者と子供をつなぐ回想法』を目的として、子供と交流しやすいと考え『遊び』をテーマに設定した。」
-

今年の7月10日の秋山地区公民館「ふらっと秋山」と、10月13日の本学保育演習室「ミトラ」での想い出カフェについて、それぞれ企画の目的やポイントや準備から当日の内容まで具体的な報告がありました。今年度のとりくみを通しての反省点は次のような内容でした。
1、何を資料としてどのようなことを子供に伝えたいのかを先に決めてから、それについて高齢者に聞くというように、子供への教育を主軸に、そこに高齢者をどう組み込むかを決めてシナリオを考案するべきだと考えた。
2、高齢者は私たちに何かを伝えるということに積極的で、子どもたちも知らないことに興味を持ってくれるということを、活動を通して肌で感じた。地域の活性化にはもちろんこれからを担う子供たちが必要である。このような活動が行われていることを実際に体験して知ってもらうことも、また意味があると感じた。
3、学芸員が世代をつなぐ役割を担うことは重要であるが、又聞きで話を詳しく伝えることは難しいため、私たちが子供と高齢者が直接交流できる場を作るというのも必要であると考えた。
-

学生報告に対し、奥村俊久さん(福岡市⽂化財活⽤課)からは口頭で、三⾓徳⼦さん(福岡市博物館運営課)からは文書でのコメントがありました。教育普及の現場に携わるお二人からの指導と励ましは、この活動にとってかけがえのないものです。
発表後は市民の方々も参加して熱心な質疑応答が交わされました。
学芸員課程2年生も真剣に聞いていました。地域回想法の体験によって学芸員の活動の可能性を探っていくという「想い出カフェ」のバトンは、先輩から後輩へしっかりつながれたようです。
本学学芸員課程には文学部3学科からの毎年20〜30名前後の履修生が在しています。とくに近年は博物館の教育普及などに携わる卒業生が育ってきています。世代間交流の失われつつある現代社会において、様々な社会課題に気づくきっかけになる活動として、「筑紫想い出カフェ」の学びがじわっと役立っているようです。(学芸員課程担当 小林記)