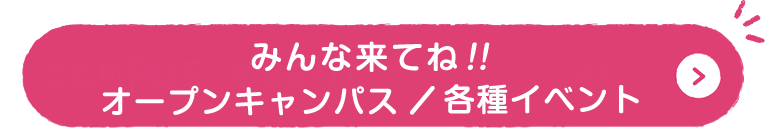福岡の女子大学|筑紫女学園大学
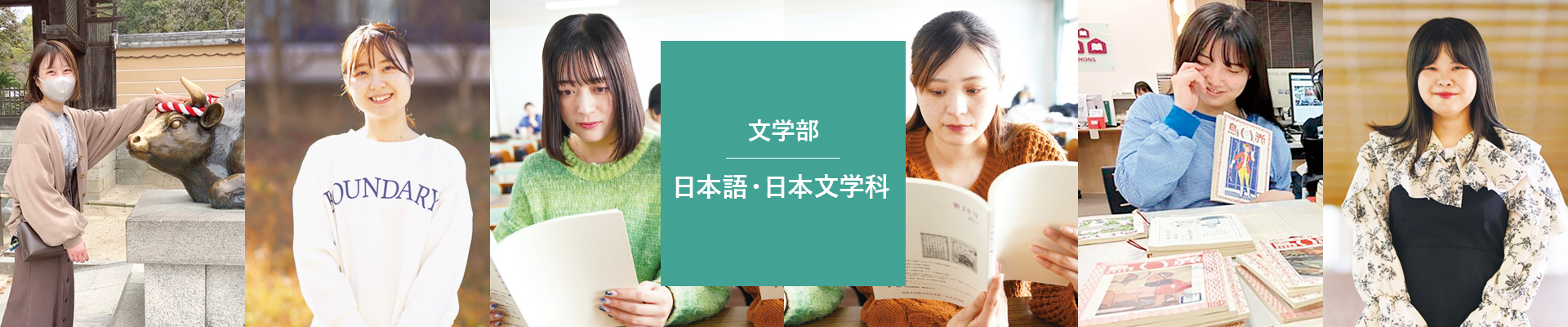
公開講座「越境する『源氏物語』」第1回「権力・政治と『源氏物語』」が開催されました
- 2024年11月03日 -
2024年度文学部公開講座「クロスオーバーアジア塾2024 越境する『源氏物語』~日本・アジア・世界~」の、第1回「権力・政治と『源氏物語』」を、10月5日(土)・筑紫女学園大学において、開催しました。この回は日本語・日本文学科の大内英範教授が担当しました。
今年発行された新しい5千円紙幣の肖像である津田梅子のエピソードに、『源氏物語』を読んで、こんないかがわしい本は好きではないと言ったというものがあります。そして津田が読んだ『源氏物語』というのが、末松謙澄による世界初の英訳でした。末松が『源氏物語』を英訳した理由を、末松自身の文章や、当時のイギリスの文学と政治をめぐる空気のようなものなどを通して考えました。また、幕末のプロイセンの対日政策との関わり、鎌倉幕府周辺で制作された写本の大きさとの関わりなど、さまざまな観点から、権力や政治と『源氏物語』との関係も考えてみました。
『源氏物語』は、おそらくはひとりの天才文学少女による趣味としての創作などではなく、少なからず一条天皇と中宮彰子、藤原道長といった、時の政治勢力や権力構造と無関係に生み出されたのではなかったはずです。誕生から約千年、権力や政治と関わりなく純粋に楽しまれているのが、案外といま、現代なのかもしれません。