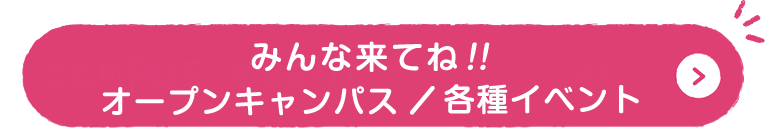福岡の女子大学|筑紫女学園大学

授業報告「多様性の国、インドネシア~インドネシアの文化、特徴や習慣を知ろう!」
- 2025年01月31日 -
1月28日の「多文化共生論」の授業では、ゲストティーチャーとして、石橋ヘルミンダワティ恵美先生をお招きしてお話をしていただきました。先生は、2004年より筑紫女学園大学で非常勤講師としてインドネシアの言語と文化を教えてくださっています。今回は、「多様性の国、インドネシア~インドネシアの文化、特徴や習慣を知ろう!」と題して、先生が日本に暮らして感じた様々な課題についてお話しいただきました。学生たちにとって、改めて自分たちの国を考え直すきっかけとなったようです。ミニレポートをいくつか紹介します。

-
- レポートその1
- 先生の話を聞いて驚いたのが、【改名することが一般的】であることだ。日本で改名することは非常に手続きが長く・細かいため名前を変える人は少ない。(苗字を変更する場合「やむを得ない事由」。名前を変更する場合「正当な事由」)しかし、日本以外の国は名前を変更する行為が一般的である。台湾の友人にも、占い師から「名前をかえなさい」と言われて実際に改名・店の名前を変更していた。日本も名前の変更手続きが簡略化されれば、キラキラネーム問題が無くなるのではないかと考えました。
-
- レポートその2
- ハラルマークを使用するために、授業を受講し、お金を支払う必要があることを初めて知りました。その方法について、中々攻めたことを行うんなだなと感じました。ハラルマークを認めるため、授業(相互理解・知識のため)・衛生チェック・現地調査が必要なのは理解ができますが、お金を支払う必要があることについては、日本人の私から見るとすこし疑問に感じました。宗教として、寄付金等が存在すると思うので、その予算内の中で活動・減額をしてもよいのではないかとも思いました。この活動を行うことで、ハラルマーク認証を得た食品が増加し、信仰している人々の生活の助けになるのではないかと思いました。先生のクイズからも、毎回食品の製造内訳確認を行うことに非常に労力かかっていることが分かったので、どうにか緩和することができないのかな、と思いました。
-
- レポートその3
- 他国で暮らす上での一番の問題は主に言語だと思っていましたが、イスラム教の人々は食べ物にも気を使わないといけないという大変さを知りました。日本に来ているイスラム教の人々に分かりやすいようにハラルマークをつけて欲しいけどハラルマークを作るにも様々な制限があってお金もかかるため、簡単ではないという現状を知りました。クイズををしてみて、自分自身は普段、食べ物に何が入っているのか意識せずに食べていることが分かりました。日本人の中で生活しているだけでは気づきにくい、外国の文化や価値観を直接教えていただきました。日本は安全という点ではいい国ですが、柔軟性が不足していると改めて感じました。日本は海外からみると非常にキラキラした憧れの国ですが、実際に来てみると外国の人にとっては沢山の壁があり、 ギャップを感じてしまうということを聞き、残念に思いました。これからの日本がどうあるべきか考えさせられる授業でした。