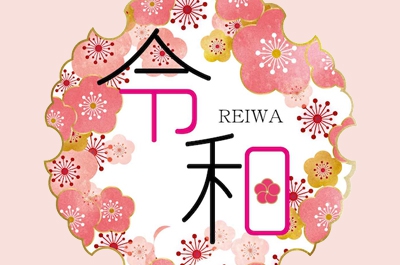各学科からのお知らせNews from Departments
【令和✿万葉✿大宰府特集】❀ 梅は咲いたか??❀
元号「令和」の典拠となった、太宰帥大伴旅人邸での梅花の宴は、天平二年正月十三日のこととされています。今日の暦では二月の初旬。さて、梅は咲いたのか??
❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿
一方、次のような歌があるのです。
烏梅能波奈 知良久波伊豆久
志可須我尓 許能紀能夜麻尓 由企波布理都々
(梅の花 散らくは何処 しかすがに この城の山に
雪は降りつつ)823番
梅の花が(雪が流れ来るように)散るというのは、いったい何処のことでございましょう。そのように言われますけれど、すぐそこに見える城の山には、まだ雪が降っておりますよ。
これは、大宰大監大伴百代(おおとものももよ)の作で、以前ご紹介した大伴旅人の歌の次に録されています。
旅人の歌はこちら
我が園に 梅の花散る 久方の 天より雪の 流れ来るかも
表現上は、花については「散る」と言い切っていて、(その花びらは)「天空から雪が流れ来るのかなぁ〜」と疑問・詠嘆で表して、見立てる形としています。あくまでも、爛漫と咲く梅園の姿を描出しています。全体の八番目、上席の人々の歌を主人として締めくくって、宴のしつらえを示したようでもあります。
これに続けて、「梅の花が散るなんて、まだまだ。あの白く舞っているのは紛れもなく雪ですよ」と、一見ネタばらしに見える歌が詠まれたのです。
三十二首の中には、百代の歌の他に二首、「雪」を詠み込んだ歌があります。
春の野に 霧立ち渡り 降る雪と 人の見るまで 梅の花散る(839番)
妹が家に 雪かも降ると 見るまでに ここだも紛ふ 梅の花かも(844番)
いずれも「雪と見まがう」ほどに「散る梅」という見立てになっています。宴の主人の修辞を承けての作法と考えることができるでしょう。
雪と梅の取り合わせは、この他に集中二十数首を数え、平安時代の和歌にも受け継がれます。「素朴・ますらお振り」などが強調される万葉歌ですが、後世の文学に通ずる洗練された姿を随所に見ることができるのです。
さて、序文で「盖天坐地 促膝飛觴(天を絹傘とし地を座席とし、膝を近づけて酒杯を盛んに回す)」と言うこの日の宴。いったいどのような光景だったでしょうか。
※ 伊藤博『万葉集釋注』(集英社文庫版など)。
三十二首全体の構成を、歌の宴として解釈されています。出席者の席次(配置)をはじめ、どの歌を承けての表現であるかなど、非常に興味深い解説がなされます。是非ご覧下さい。
❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿
大宰府に通って40年の経験からすると、2月は寒い!というのが実感です。
2017年には、ちょうどその頃に雪が積もりました。梅が咲き初める頃、まだ雪が舞う日がある、という土地柄です。北部九州は、意外と寒いのですよ。
今年は暖かい方で、左は、先週(7日)の都府楼付近の梅です。三分咲きというところでしょうか。
この日はメジロが来ていました。
天平二年のその日は、さて 梅は咲いたか 散り紛うたか・・・
小野 望(日本語・日本文学科教授)
No.83 **********
日文 ❀❀ 令和 ✿ 万葉 ✿ 大宰府特集 ❀❀